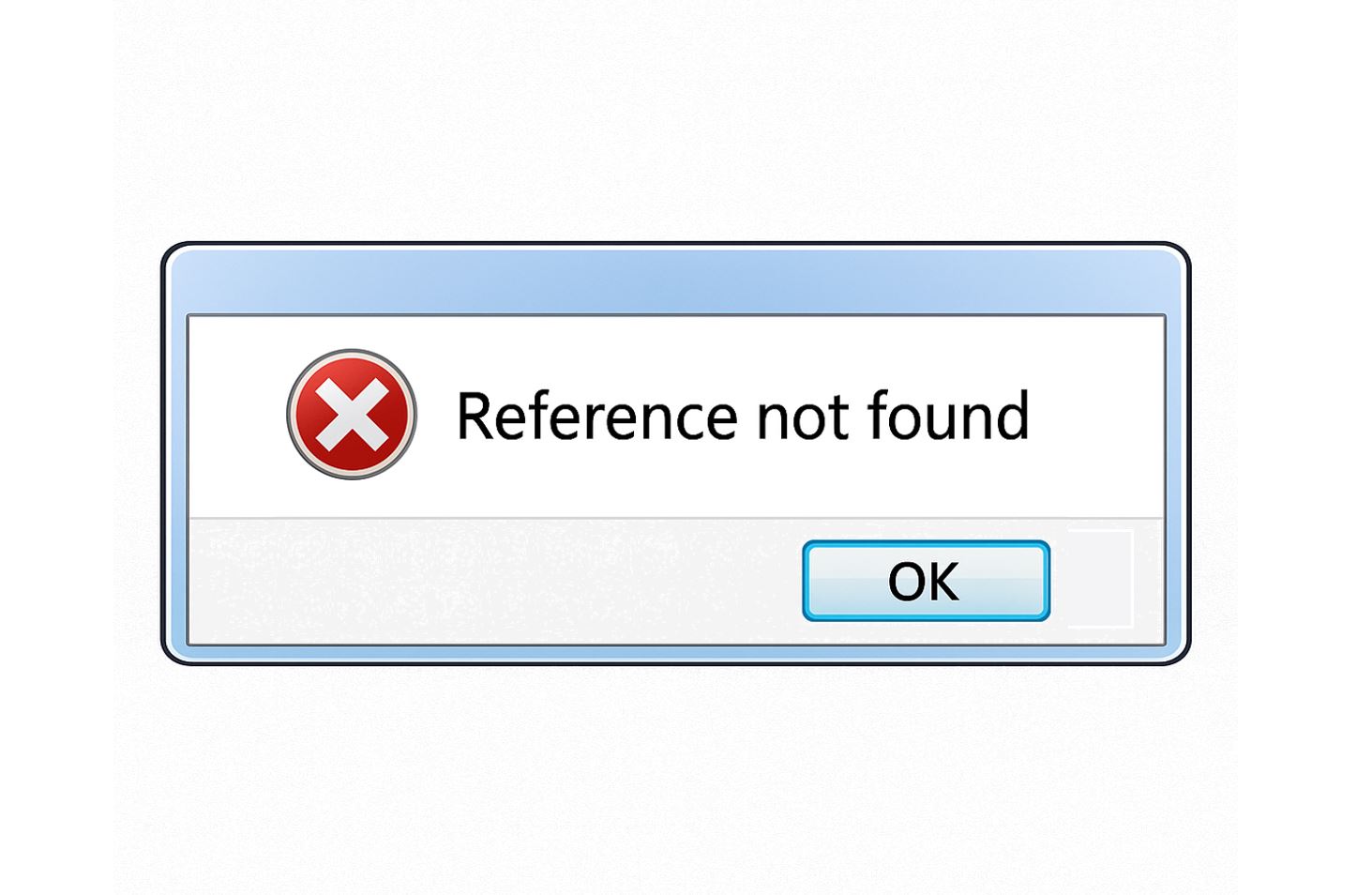
(こちらは、日本人駐在員の方々向けのJCO「グローバルマネジメントの基礎」シリーズの第2弾です。1回目はこちらから)
多くのグローバル企業では、「エスカレーション(escalation)」という言葉がごく普通によく使われます。多くのマネジャーにとって、それは「責任を持つこと」を意味します。つまり、自分の権限で解決できない問題が発生した場合、一つ上のレベルの責任者に報告し、迅速かつ効果的に解決できるようにするという考え方です。エスカレーションは、ビジネス上の課題、人事関連の問題など、さまざまな場面で使われます。
しかし、日本的な視点から見ると、このような行動はどこか居心地の悪さを伴うかも知れません。昔から日本のビジネス文化では、調和、自制、そして根回しといった、公にことが為される前に水面下で徐々に合意を形成するプロセスが重視されてきました。
そのため、「何かを積極的かつ公式にエスカレーションする(次のレベルに託す)」という行為は、「諦めるのが早すぎる」「内部の問題を外部に晒している」と受け取られかねません。
興味深いことに、日本語には、このような文脈で使われる「to escalate」という動詞に直接対応する表現が存在しません。唯一の近い表現は「エスカレートする」ですが、この場合は、「(何か)が発展する・悪化する」という意味で、先に挙げたような意味合いではありません。
日本語では、同じ状況をより受動的に表現する傾向があります:
- 発展する(to develop into something)
- 深刻化する(to become serious)
- こじれる(to get complicated)
たとえば法務や人事の場面でも、「問題が法的措置に発展した」というように、問題そのものが自然に展開していくように表現されることが多いのです。つまり、そこでは「誰が行動したのか」という主体が消え、問題と解決が自然に進んでいくように表現されます。
多くの日本企業では、英語の 「escalation (エスカレーション) 」という言葉は、別の意味で使われています。つまり、ある部署が将来起こり得る間題について、本社や他部署に知らせることを指します。 しかし、これは個人が行うのではなく、チームを代表して行われます。潜在的な問題を、できる限り早い段階で上位レベルが把握・監視できるようにするためです。 その意味では、むしろ「事前警告システム」に近いと言えるでしょう。
もちろん、実際には欧米的な意味の「エスカレーション」を行う(=現状レベルで解決のつかないことを、上位レベルの処理事項とする)日本人社員もいます。しかし、この言語的特徴は、「忍耐」と「集団での解決」を重んじる考え方を反映しているのではないでしょうか?
グローバルな組織においては、この傾向が行動の遅れにつながる場合もあります。日本人が「我慢と敬意を示している」つもりである一方で、外国人の同僚は「何も言わない=責任感がない」と感じているかも知れません。
グローバルな文脈において、調和(harmony)と責任説明(accountability)のバランスを取ることは、日本人ビジネスパーソンにとっての課題でしょう。
エスカレーションは対立を意味するものではなく、問題が大きくなる前に「適切な人に助けを求める」行為です。
早めに行動することは、決して非難ではなく、責任を果たす行為なのです。
JCOエキスパートからの地域別アドバイス
オリヴィエ・ヴァン・ベネデン(JCOマネージングディレクター・欧州)
「ヨーロッパでは、より平等主義的な文化(ゲルマン系)では、事実に基づき、客観的で冷静に問題をオープンに話し合う傾向があります。
一方で、より階層的な文化(ラテン系・東欧諸国)では、組織のヒエラルキーや正式な報告ルートを尊重しながら、非公式な話し合いで解決を図る傾向があります。」
サスキア・ロック(JCO USA支部マネージングディレクター)
「米国では、エスカレーションはプロ意識と責任感の現れと見なされます。
これは騒ぎ立てたり責任を転嫁することが目的なのではなく、適切な人が早期に対応できるようにするためのものです。
特にスピードが求められる環境や、重要な局面においては、早い段階で問題を報告することは、弱さではなく、むしろ強さとみなされます。それは「注意を払い、責任を持ち、チームや会社全体を不要なリスクから守る」姿勢とみなされます。
エスカレーションは、透明性・スピード・明確な責任分担を重んじる文化の一部なのです。」
太田理恵(JCOシニアトレーナー/コンサルタント・APAC支部)
「多くのアジアの文化においては、集団の調和を保つことは社会的義務として極めて重要視されています。
そのため、直接的な対立を避け、信頼できる上位者が仲介して問題を調整し、均衡を取り戻すという方法が一般的です。
アジア・太平洋地域における真のリーダーシップとは、「迅速にエスカレーションすること」ではなく、静かで敬意ある形で解決を図る力にあります。これこそが、人間関係とメンツを維持する鍵なのです。」
これらのトピックは、世界各地で開催しているJCOオープンワークショップ(公開講座)で詳しく学んでいただけます。



